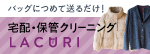上田商店ニュース
上田商店が発行しております FAXニュースをWEB版でご覧いただけます。
WEB版 上田商店ニュース
年末・年始商戦の準備はいかがでしょうか
今年も40日余りとなりましたが、年末・年始商戦の準備はいかがでしょうか。東日本大震災をはじめ、紀伊半島の台風被害、海外ではトルコの地震、タイの洪水と天災の多い年だったように感じます。
今回も、サークル会メンバー各自で、様々な情報を持ち寄り話し合いました。昔からの「待ちの商売」の意識を転換し「モノを売る商売」に考え方を変える必要があるように思います。売るためには、どうすれば売れるのか考え、勉強や努力も必要になります。
上田サークル会 会長 上田 良堂
今回も他業種情報を含め提案をまとめました。
まめなサービスと対応を
保険会社の外交員が定期的に訪問し、情報チラシを配布するなど、こまめなサービスを行っている。
クリーニング店も、定期的に手入れ方法や、家庭でできるシミ抜きなどの情報サービスを行ってはどうかと感じる。パソコン通信だけでなく、最近家庭に普及してきたFAXを活用(要本人確認)するのも一つの方法だと思う。主婦のじゃまにならない、読んでいただける確率の高いFAX通信。同じ情報を店頭に置き活用する。定期的に行い継続することで、お客様から信頼を得られ、囲い込みにも繋がるのではないかと思う。
富裕層向けの宅配クリーニング
雑貨輸入販売の某社(東京都)がインターネットで受注する宅配クリーニングサービスを開始した。ザ・ランドレスのファブリック製品を使って洗い、仕上げたものを宅配するシステム。徹底した"こだわり"重視のスタイルで、3年前から提携輸入販売している米国のファブリックケア会社ザ・ランドレス※の製品を使用。洗いと仕上げはパートナー契約の業者が行う。既に宅配クリーニングは市場と構築してきているが、よりファッション性の高いコンセプトで事業の新展開を図る。
(日クリ新聞 第1619号より要旨抜粋)
※ザ・ランドレスは、名門大学で研究を重ねた2人の女性が、ラグジュアリーブランド商品開発会社を04年にニューヨークに設立。
二極化された欧米に比べ、日本では全体として中間層重視で歩んできたように思う。ターゲットを絞り細分化する事を考えてもいいのではと思う。
「モノ」を売るのではなく「コト」を売る
「食物」を売るのではなく「食事」を売る経済的価値の訴求に成功した事例。
シチューの販売コーナーで、(1)単品だけをアピールした陳列方法。(2)鳥もも肉や玉ねぎなどの他の食材も記して「今夜はシチューにしませんか?なんと一皿100円」とメニュー全体で訴求する方法を比べてみた。1週間ずつ陳列した結果、(2)の方が立ち寄り率、検討率、購買率すべての面で上回った。
(「戦略経営者」2011年2月号より要旨抜粋)
これを読み、ちょっとした工夫が面白いと思った。クリーニングも安さの訴求だけでなく、サンプルを展示するなど、家庭での洗濯に関するシーンを絡めて提案することで、消費者の捉え方が変わってくるのではと思う。
地域に愛され必要とされる店
高知県で1961年創業の某社は、四国有数のスーパーマーケットに成長。「食」を中心とした暮らしの提案を行う店づくりに取り組んでいる。
地域の活性化だけでなく、地産地消によるCO2の削減にも貢献。「食材販売」ではなく「食事提供」という店づくり。97年よりの無条件返品・交換サービス。希望サイズ・量での小分け販売。
また、親子水泳教室やマラソン大会などの支援にも積極的。食育活動にも取り組んできた。「損か得かではなく、正しいか否か」を取り組み指針とし、地域住民に愛される、必要とされる店づくりをやっている。
クリーニングも、地域に根を張る店づくりがもっとうまくできないものかと感じた。
家庭ではできない意外性を
「デカ盛りメニュー」が女性を中心に人気を集めている。大型ハンバーガーやジョッキ型のプリン、野菜大盛りちゃんぽんなどだ。外食時はダイエットを一休みして、ボリューム感や意外性を楽しみたい気持ちを汲み取っているとみられる。
という日経新聞の記事を読んで、クリーニングでも固定観念を捨てたアイデアで、楽しいサプライズができないものかと感じた。家庭ではできない驚きや楽しみ…何かありそうな気がする。
地域ぐるみでのパフォーマンス
東灘の35店舗が協力し、最寄り駅から専用バスを終日フリーパス、1日14便運行。約1ヶ月間、土・日・祝限定で行われていた。色々な特典が付いている。地域ぐるみで、喜んでもらう努力をしている。
クリーニングも地域に密着した業種、コラボレーションを含めて考え、行動すべきだと思った。
店の特徴、特長づくりを
激安系回転すしチェーンは戦国状況。その中でも店舗数トップのチェーン店は"安さ"、2位は"品質"重視、3位は"子どもが喜ぶ店"と各チェーン店に特徴がある。過去の回転すしのイメージは、様々な努力で大幅に良化し、消費者に認知されたように感じる。
クリーニング店も、価格・品質・来店しやすい店づくりなどの特徴や特長があってもいいと思う。店をあげての努力が必要だと思った。
クリーニングについての消費者の意見
店を選ぶ基準がネットにのっていました。
参考になればと思います。(要旨抜粋)
街中に乱立するクリーニング店。
店構えも料金もまちまちだけど、
一体どうやってお店を選べばいいのかな?
◆クリーニング店を選ぶ基準
(1)キレイなお店を選びましょう
清潔が売りのクリーニング業です。お店側がキレイでないのでは話になりません。まず店内の照明が明るいこと。そして清潔感があること。軽いBGMなんかが流れている店もいいですよね。
(2)料金でお店を使い分けましょう
普段着や作業着などは高料金のクリーニング店でなくてもいいのかもしれません。逆に大切な衣料、フォーマル衣料などは必ず高料金のお店に出すようにしましょう。仕上がりがまったく違いますよ。
(3)カウンターの対応で決めましょう
これもどの商売も同じで、カウンターはお客様との接点です。明るく笑顔で、はきはきとした応対は言うまでもないことですが、その他にも対応が明確で、顧客ニーズ(A)をきちんと聞いてくれること。また家庭での衣類管理などの相談や、何かトラブルになった時に親身に話を聞いてくれるカウンターの応対が大切です。
特にクレーム(B)などでは、ろくに話も聞かずに「クリーニングのせいではありません」「ご不満なら生活センターに行ってください」の繰り返し、こういった店には出してはなりません。
(4)お勉強をしているお店かどうか
どのお店でも業者が参加している、クリーニング業界なりの研究グループなどの会員証やステッカーが店内に貼ってあったりします。これは技術を売り物にする業者の勤勉さの裏返し。そういった部分も、技術の確かさでお店を選ぶポイントの1つになります。
上記意見の(A)(B)に対しての感想
(A)受け渡しだけでなく、新商品の繊維情報や家庭での
注意点など衣類に関しての情報提供が大切だと思う。
(B)クレームは、お客様を失う事だけでなく、
逆に信頼を得るチャンスでもあると思う。
本部のしっかりとした対応策が必要かと思う。
上田商店ニュース
製品紹介
会社概要
HOME | 上田商店はお約束いたします! | 製品一覧 | クリーニングQ&A | 上田商店ニュース |
ご質問コーナー |
セミナー開催|メディア掲載・登場|サイトマップ | メール | 会社概要 | メッセージ | 社員紹介 |
特定商取引に関する法律に基づく表記 | FAXニュースお申込み |
Copyright (C) 2012 株式会社上田商店 All Rights Reserved .
Web Designed by Altstarr Inc.